
事業化グループ
グループディレクター
松本 毅 Matsumoto Takeshi
オープン・イノベーションの拠点を、神戸につくる。
ニーズとシーズを高いヒット率でつなぎ、新事業化を加速しています。
私たちは、健康・ヘルスケアの分野で次々と新しいビジネスを創出していくために、さまざまなかたちで事業化支援機能の整備を行っています。オープン・イノベーションには、大きく2つのかたちがあります。ひとつは、HOW TO DO。たとえば、「この製品に、こんな性能を持たせたい」というニーズがあるものの、どのように(=HOW)達成すればいいのか分からない。そこで、ギャップを埋めるためにシーズを持った人を社外から見つけてくる。自社のニーズをオープンにすることで革新的な製品が生まれたという成功事例が、世界中で報告されています。事業化グループでは、参加企業のニーズに合うシーズを見つけてきて双方がメリットを得られるような「ニーズプル型のマッチング」と「シーズプッシュ型マッチング」イベントを開催。高いヒット率でマッチングが生まれています。もうひとつは、WHAT TO DO。「健康・ヘルスケアの分野で新事業(=WHAT)をしたいけれど、社内で議論しても良い事業アイデアが出てこない」という場合です。私たちは、海外のデザイン思考のモデルケースにならい「IIBサロン」を設けて、研究者や起業家が新たなアイデア、イノベーションの種を発掘するための場を提供しています。 神戸医療産業都市には、理化学研究所をはじめ、素晴らしい研究シーズが生まれる土壌が既にあります。研究者自ら用途仮説を考えて、より“実用”の方へ目を向けて情報を発信する「シーズ発表会」という場も設けています。さらに、リサーチコンプレックスの参画機関による短中期的な実用化を目指す活動を「モデルプロジェクト」に設定し支援しています。より成果の出る、より成功確率の高いマッチングイベントを練り上げて、将来は「世界のスタートアップによるイノベーションピッチコンテスト」「グローバル・ニーズプルマッチング」を実現したいと考えています。事業創造を強靭に支援するプログラム群を整備し、ここ神戸に、世界に先駆けた「グローバル・オープン・イノベーションの拠点」をつくり上げていきます。
事業化グループの「事業化支援機能」
「事業化グループ」の主な機能は、5つあります。
①マッチング機能:研究・技術シーズから事業創出を加速するためのシーズプッシュ型・ニーズプル型
②マーケテイング機能:デザイン思考を実践するリビングラボ・プロトタイピング
③インキュベーション機能:オープン・イノベーションによるベンチャー・新規事業創出を支援
④資金調達・投資機能:ベンチャー企業や事業推進に必要な資金調達をサポート
⑤目利き機能:シーズや技術の市場性、ビジネスの収益性などを評価し、事業化をコーディネート
2016年12月に研究者やベンチャー企業が自分たちの新技術・新事業を発表する「シーズプッシュ型」のマッチングイベントを開催。第1回目にして10チームすべてがマッチングに成功しました。今後もネットワークと情報を保有する外部機関とも連携をはかりながら、「事業化支援機能」を強化する体制を整えていきます。
-

事業創出
オープンイノベーション&ネットワーキング
-

シーズプッシュ型
ベンチャー企業とのネットワーキング
-
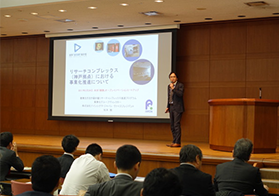
ニーズプル型
未来「健康」オープンイノベーションミートアップ analysis of gene expression)をはじめとするトラスクリプトーム解析に威力を発揮します。バイオマーカーを用いた診断法の開発などに活用されています。
Future CenterとLiving Lab
欧米では、「デザイン思考」という考え方にもとづいて“ニーズのあるシーズ”を見つけ出すための仕組みとして2つの場が発達しています。「Future Center」と「Living Lab」です。Future Centerは、多種多様な人が集まり対話するセッション・ワークショップスペースであり、イノベーションの種や創造活動を引き出す場。Living Labは、生み出した商品・サービスのプロトタイプを多くの人に試してもらい、フィードバックを得ながら共創していく場です。事業化グループでは、理化学研究所融合連携イノベーション推進棟内にセッション・ワークショップスペース「IIBサロン」を、神戸・三宮にLiving Lab機能を有するiKAfE(あいかふぇ)を整備しました。共にイノベーションを加速し、ネットワークを形成する場として機能していきます。

『アイデア創出の場』として、理化学研究所 融合連携イノベーション推進棟(IIB)の6階にセッション・ワークショップスペースを開設。
未来的な視点で創造的な対話からイノベーションの種を生み出す場所です。



